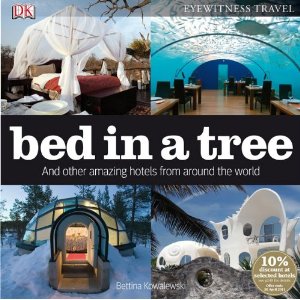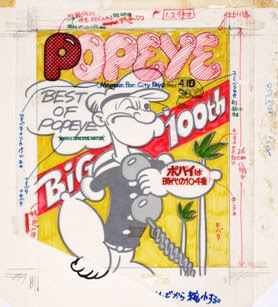2008年に出版した『BOROつぎ、はぎ、いかす。青森のぼろ布文化』(小出由紀子さんとの共著)のコレクションを実際に見て、触って体感できるユニークなミュージアムである、浅草のアミューズ・ミュージアム。芸能プロダクションの運営ということで、インテレクチュアルな芸術ファンには色眼鏡で見られがちだけど、あれだけの収集品を見て触れるというだけで、お堅い公立美術館よりはるかに刺激的だと思います。
そのアミューズ・ミュージアムで、常設のBORO展と並んで、11月11日から始まっている開館1周年特別展が『LOVE! HANDMADE 手しごと刺繍展』。なんだかフェミニンなタイトルですが、中味はなかなかどうして! 青森県南部地方で明治大正期、貧しい農家の女性たちが身につけたタッツケ(仕事着である股引)の逸品を並べた、非常に珍しいコレクションです。
タッツケとは、相撲の呼び出しなどが着用している膝から下が細く仕立てられた袴「裁着(たちつけ)」が転じたもので、青森県南部地方では女性の仕事着である股引(ももひき)の呼称だが、女性の下肢にこれほどの刺繍が施された衣類はこの南部地方に固有のもので世界的にも稀なものだ。
南部地方は青森県を二分する太平洋側の地域である。雪が少なく緑豊かだが、土壌が稲作に向かない畑作地帯で東北の中でも特に貧しい地域だった。木綿は高級品だったので衣類はもっぱら麻布が中心。貧しさゆえ衣類を染める藍さえも多量に使うことができず、淡い浅葱色の染めが主流だった。
また、この地域は北東風(ヤマセ)が強く人々を苦しめた。寒冷で過酷な風土は衣服にも表れ、上衣はもちろん下衣にも保温と補強のために刺し子がほどこされた。下衣は上衣よりも損傷が激しいため、タッツケは特に丁寧に手刺繍された。過酷な環境が固有の風土的美意識を育み、浅葱色の麻布に貴重品だった木綿糸を縫いつける刺し子の技の粋が集められた。それが「南部菱刺しタッツケ」である。
寒村の農民の仕事着というと、現代の我々はついつい「ボロボロの作業着」だと思い込んでしまうが、当時の農村での仕事着は単なる作業着ではなく人が集まる場所に着ていく衣類でもあるので、現代でいうOLのオフィスウェアやビジネススーツに近い感覚の衣類だった。特に男性同様に畑仕事などの労働を行っていた若い女性にとって仕事着は、パーティーウェア(晴れ着)ではないものの決して単なるワークウェアではなく、美しくありたいと精一杯の工夫を凝らした装いでもあった。
もちろん機能的なデザインとなっており、膝上は畑仕事の時に動きやすいようゆったりと、また膝下は害虫に刺されないため体にフィットするよう極端に狭くなっている。
このジョッパーズのようなシルエットの裏地の傷んだ部分は、つぎあてされ補強され新たな合わせの妙をみせている。全面に施された刺し子は、娘たちの技を競うものであり、美しくありたいと願う心の発露であった。
そんなに昔のことではない。かつては日本でも自分や自分の家族の衣類を一家の女性たちが自ら作ることは日常的なことだった。豊かではない暮らしの中、わずかな端切れ布や短い糸もとても大切にし、手に入るものを最大限工夫して、美しくありたい、健康でありたい、と願った想いが、これら美しい仕事着に残されている。これら一般女性の技術と想いをご覧ください。
いまや、ほとんど出口のないような閉塞感におおわれたハイ・ファッション界に較べて、こうした日本でもっとも貧しかった地域で百年以上前に生まれた衣装が、どれほど自由に、しかもシャープに映ることか。
展覧会は4月3日まで開催中。浅草寺のすぐ脇とロケーションも最高なので、ファッションに興味あるひとも、デザインに興味あるひとも、浅草に興味あるひともぜひ足を運ぶべし。しかしこういう貴重な展覧会を、こんな小さな民間のミュージアムにやられてしまうことを、おしゃれなデザイン・センターや公立の大ミュージアムさんたちは、もっと恥ずべきじゃないんでしょうか。